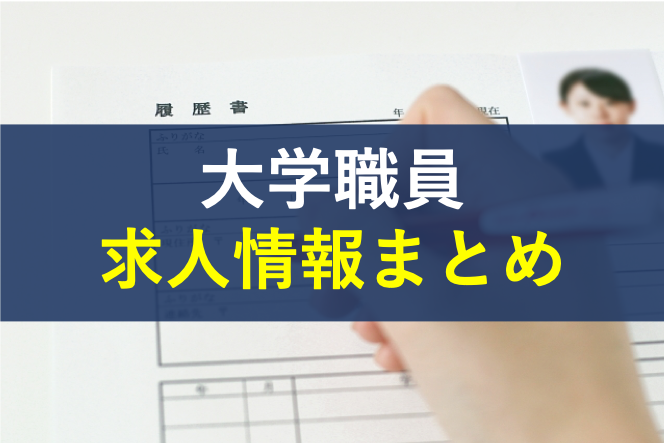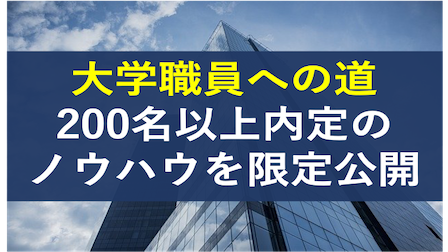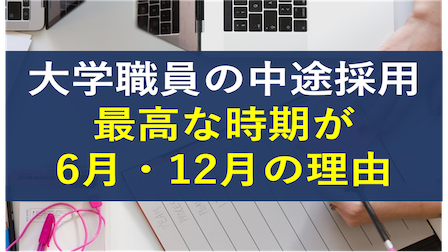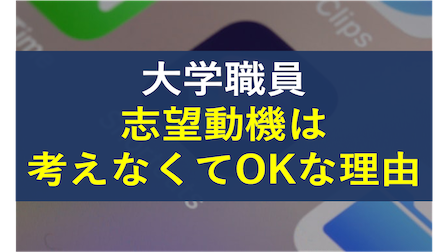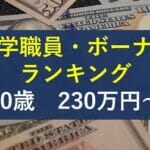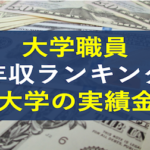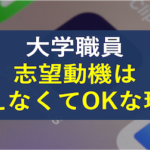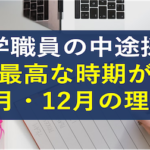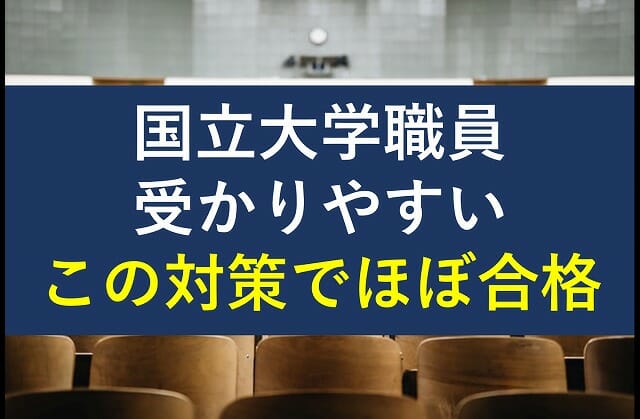

そんな疑問にお答えします。
本記事の内容
- 国立大学職員が受かりやすいって本当?
- 国立大学職員と私立大学職員で受かりやすい違いってある?
弊ブログでは2022年5月時点で20名、累計277名が大学職員へと転職成功しました。
弊ブログだと、多くは私立大学職員へと転職しており、それは大学職員の年収は私立大学職員のほうが圧倒的に高い(日本全国の私立大学職員平均で734万円!)為です。
ただ、地方によっては国立大学職員が一番マシな就職先であったり、都内でも安定的に募集しているのが国立大学職員だったり(MARCHでもほぼ募集しない大学もある)するので、受かりやすい国立大学職員は押さえておいたほうが良いのは事実です。
例えば、最近積極的に採用している東京医科歯科大学であれば、2019~2021年の3年間で61件の求人を公開して募集しており、毎月求人が出ている計算になります。 最新の大学職員求人一覧を見る
そんな国立大学職員は、受かりやすいというよりは、安定して求人があるということがメリットであり、私立大学職員を第一志望にしながらも、国立大学職員は一応押さえとして受けておくという感じでもOKです。
実際、弊ブログでも年収1,000万円の大学職員はやめとけという人もおり、必ずしも年功序列で誰でも年収1,000万円の私立大学職員が正解とは限りません。
国立大学職員が受かりやすいかどうか考えるために、よく一緒に比較されやるい私立大学職員についても学びながら、一度この記事でおさらいしてみてください。
[st_toc]
国立大学職員に受かりやすい理由|私立大学の大学職員との違い
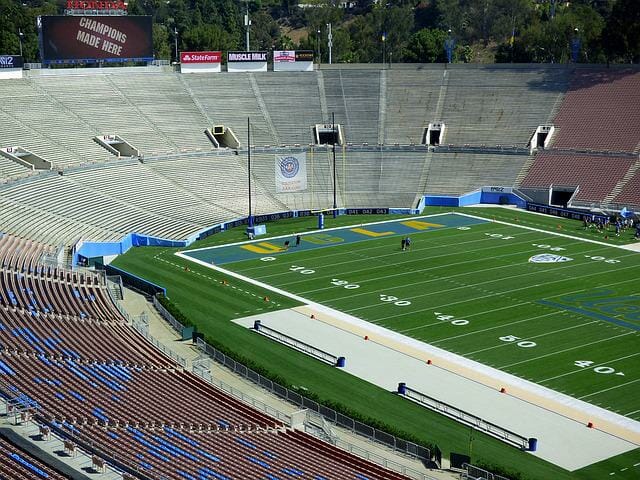
国立大学職員が受かりやすい理由を知るには、まず私立大学職員との違いを知っておく必要があります。
弊ブログでは、2022年5月時点で20名、累計277名が大学職員へと転職成功していますが、その合格者の多くは私立大学の専任職員です。
転職活動をこれから大学職員に絞って始めてみようという人は多いですが、無料の相談用LINE@に来る質問や相談についても、そのほとんどは私立大学職員になりたいというものです。
それは、国立大学職員と私立大学職員では年収に非常に大きな差があるからというのが、最大の理由です。
例えば、東京大学や京都大学勤務の事務職員と、早慶・MARCH勤務の事務職員の年収を比較したとき、それは非常に大きな年収格差となります。
東京大 677万円(44歳)
京都大 642万円(43歳)早稲田 1,141万円(45歳)
慶応 826万円(45歳)
中央 1,163万円(45歳)
明治 1,192万円(45歳)
入試では日本で最上位の東大・京大であったとしても、年収は公務員準拠程度であり、45歳の事務職員の平均年収は700万円に届きません。
大学職員の年収で700万円というと、大手私立大学職員だと30歳前半で十分に到達する金額であり、年収格差は圧倒的に国立大学職員<私立大学職員なのです。
そのため、あえて最初から国立大学職員が受かりやすいと思って志望する層は、ご自身のスペック的に大手私立大学職員は厳しいけど大学職員になりたいという人も多く、一流企業勤務が出願する大手私立大学とは異なります。
なので、国立大学職員のほうが年収が圧倒的に低いので、私立大学職員よりも受かりやすいと言え、そのあたりはご自身の考えや合格可能性と相談して頂くのが、一番正解です。
国立大学職員に受かりやすい志望動機とは?

弊ブログからは、累計275名以上が大学職員へと転職していったのですが、大学職員に合格しやすい志望動機というのは間違いなく存在します。
例えば、大学職員の志望動機を書いて下さいという設問が大学職員のオーソドックスなエントリーシートとしてあるのですが、
スーパーの販売員として日々接客をしていく中で培ったコミュニケーション能力や傾聴力が、教授・職員や大学生と関わっていく大学職員という仕事で活かせるのではと感じ、興味を持った。
という趣旨のことを多くの人は書くのですが、完全に間違っています。
「大学職員の志望動機を教えてください」・「大学職員に興味を持ったキッカケから、志望動機を記述してください」という設問について、90%ぐらいの人はご自身の自己PRから書き出して道を間違えるのです。
というのも、国立大学職員に受かりやすい志望動機・私立大学職員に受かりやすい志望動機ともに、本当に重要なのは「その大学特有の強みに対して、自分自身のどんな能力が活かせるか」であり、その具体性で全てがきまります。
ただ、90%の多くの人は、大学職員という仕事を理解できておらず、なぜその大学でないと自分は転職するのが駄目なのかという質問に端的に答えることができないので、不合格になっていくのです。
大学職員という仕事は、ノルマや目標がない仕事なので、前職で仕事ができた、できないとか売れてる売れてないとかは一切関係ありません。
累計275名以上が大学職員へと転職していったのを見ていると、大学職員に合格できる人というのは、「大学職員という仕事を理解しつつ、その大学の取り組みを具体的に話せている」ということです。
大学職員転職で失敗しがちな志望動機
共通点
=生半可な知識では大学毎に差別化できないモノ就活支援
→その大学独自支援を探すの難しい奨学金
→財源増加策とセットなら🙆学費払えない人への支援
→払えないものは払えない学生支援
→具体的内容を定義化する必要有。全般なら抽象的になる...— 暇な大学職員@2022年20名・累計277名が転職済 (@univadm) May 25, 2022
共通点
=生半可な知識では大学毎に差別化できないモノ就活支援
→その大学独自支援を探すの難しい奨学金
→財源増加策とセットなら🙆学費払えない人への支援
→払えないものは払えない学生支援
→具体的内容を定義化する必要有。全般なら抽象的になる...
なぜか90%ぐらいの最初の段階で大学職員の志望動機・エントリーシートで不合格となる人は、現役大学職員でも差別化できないことを書いて散っていくのです。
実際、弊ブログから大学職員へと合格した人でこのテーマを書いた人は5%もおらず、実は合格するテーマは研究支援やリカレント教育、リメディアル教育をヒントに、人と違う志望動機を完成させています。
人と違う志望動機をショートカットで完成させ、面接対策に注力したい場合に備え、基礎力できた人専用のnoteも書き出しました。
>>累計277名(2022年5月時点)が合格した大学職員転職で、合格確率を高める志望動機の組み立て方と業務理解のコツ
国立大学職員は独自採用で受験するのが1番受かりやすい

どうしても大学職員に転職したいので、本当に穴場の国立大学職員が受かりやすい受け方を教えてくださいと、大学職員転職専用の無料LINE@で聞かれたことがあります。
これの答えですが、国立大学職員に最も受かりやすい、各大学の独自採用試験を受験するのが正解です。
国立大学職員の転職の場合、統一試験を受験し、通過したら各志望する大学の面接に進む方法と、各大学が独自に採用試験を実施している、独自採用方式が存在します。
国立大学職員に受かりやすいのであれば、受けるのは「独自採用」のみでOKです。
その理由は、国立大学職員の転職において、統一試験を受験する=一定の学力や対策が必要であり、公務員試験対策をしている人たちが大量に受験してきます。
私自身、残業時間毎月100時間前後の社畜系民間企業から、ノルマや目標が無い大学職員になりたくて、転職を考えたのですが、国立大学職員に受かりやすいからといって統一試験を受験するのは無理だという結論に至りました。
そのため、弊ブログから大学職員に合格した275名以上は、95%以上が統一試験ではなく、独自採用試験での合格者です。
独自採用試験のほうが、面接重視で転職希望者との親和性も高く、ペーパーテストの点数だけで採用するのはやめようと大学側も考えている確率が高いので、合格可能性が統一試験よりも大幅にアップします。
そもそも勉強が全くできないFラン高校卒なので、塩分濃度計算の分数の計算すらできません。
そんな勉強ができない自分自身でも、ワンチャンで高給の大学職員を狙うには、勉強以外の部分で勝負する必要があると考え、独自の理論で大学職員に合格できる志望動機を考え始めました。
そうすると、まず第一関門として勉強で着られる統一試験を受験する必要は全くなく、面接対策で決まる可能性の高い「独自採用」がもっとも合格に近いと感じたのです。
もちろん、私立大学職員には統一試験はありません。
各大学がそれぞれ、自分なりの方法で私立大学職員を募集しており、その私立大学こそが最も年収が高くて国立大学職員よりも休みが多いという業界のスタンダードです。
そのため、国立大学職員が受かりやすいとはいいつつも、やはり誰でも年収1,000万円でノルマや目標無しの私立大学職員も一応狙っておくのが良いと思います。
国立大学職員は受かりやすいのは確かですが、やはりエージェントを活用したり、転職サイトでの広報がうまいのは私立大学なので、通常の民間企業転職と同様に、私は転職エージェントも利用していました。
このブログから407人が大学職員に内定しました
2024年4月までに
大学職員を目指せるエージェントのまとめ
弊ブログからは、2018〜2024年で407名が大学職員へと転職しました。
大学職員の転職は情報戦です。自分の知らないうちに求人が出ていることを避けないといけません。
弊ブログでの実績のある、合格者がみんな使っていたエージェントは2つだけですので、シンプルです。
早めの登録と活用がポイントになります。
大学職員に転職できるエージェント
リクルートと並ぶ実績のあるエージェント