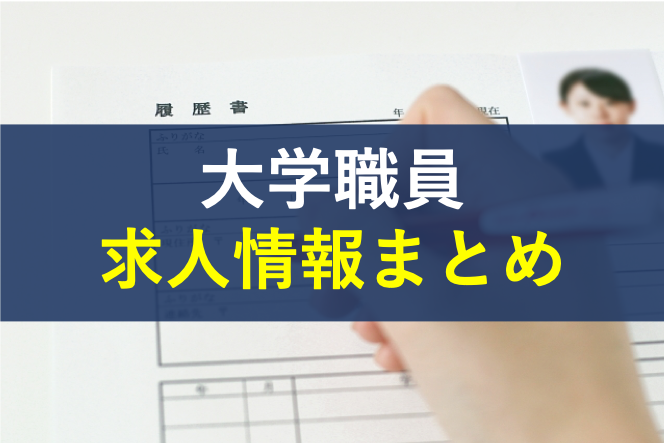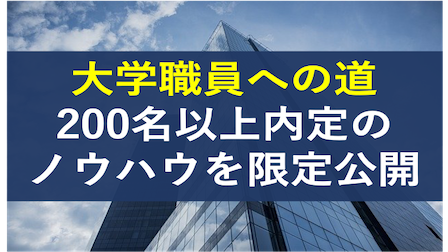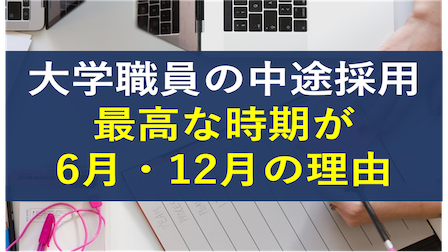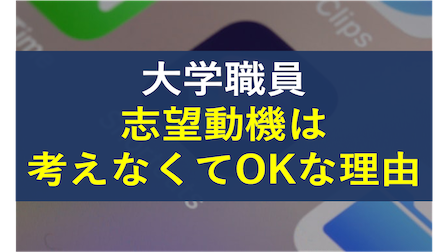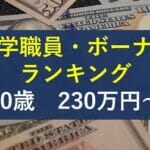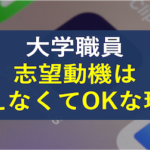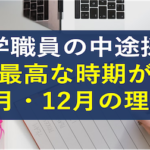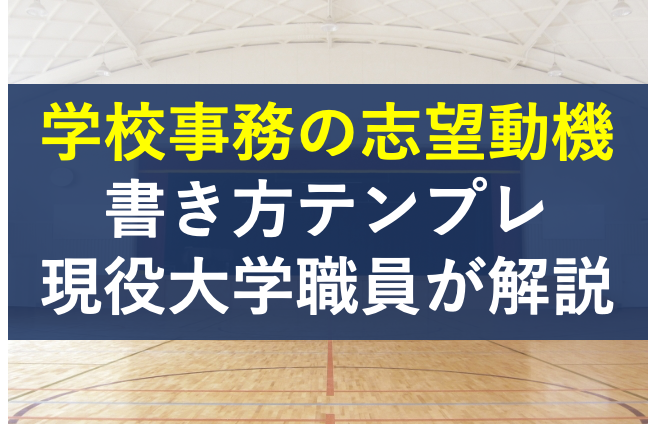

そんな疑問にお答えします。
本記事の内容
- 学校事務ってどんな仕事をするの?【現役大学職員が解説】
- 学校事務で働くメリット・デメリット
- 学校事務の志望動機の書き方
いまの仕事が嫌だから転職したい!
とも思ったとき、どんな仕事が転職先として候補に上がるでしょうか?
民間企業勤務のあなたから見て、大学職員って楽そう?
— 暇な大学職員@今年89名・累計165名が転職済 (@univadm) October 17, 2020
まあ、大学職員や学校事務って楽そうなイメージありますよね。
一般的には、学校事務(=小中学校勤務の仕事)、大学職員(大学を持つ学校法人勤務)とされますが、どちらも学校で働く民間企業には無い緩さがありそうです。
私自身、年間総残業時間1,200時間の企業から転職したら、年間の総残業時間が30時間ぐらいになって、超絶快適でした。
年収も悪くないですし。
-
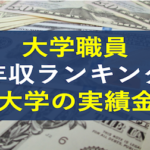
-
大学職員の年収ランキング|現役が解説する内部情報【2023年12月版】
続きを見る
今日は、そんな学校事務(小中学校勤務や大学勤務)について、転職希望者向けの志望動機を中心に書いてみました。
弊ブログからは2020年だけで89名が大学職員へと転職しているのですが、志望動機などはコピペOKです。ブックマークなどして自由にお使いください。
[st_toc]
学校事務として働くメリット・デメリットを現役大学職員が解説

私自身、毎月の残業時間が100時間を超える社畜系民間企業から、大学職員へと転職しました。
今の仕事が朝早くて夜も遅いうえに、営業のノルマややることが多すぎて早く辞めたいと思ったとき、「とにかく楽な仕事がしたい」と考えたのがキッカケです。
精神的に楽な仕事がしたいなーと思ったら、まず思い浮かぶのは公務員ではないでしょうか。
ただ、公務員のネックは公務員試験への勉強をしないといけません。
私の場合、偏差値40前半のFランク高校を卒業していたので、そもそも頭が良くない。
英語もTOEIC300点前半が最大値なので、勉強して受かる可能性は低いことが判明しました。
勉強しても受からないと知って、まず思ったのは、「公務員は年収が低いし、、、」という逃げの思考。
そうなると、勉強しなくても受かるノルマが無くて精神的な楽な仕事=大学職員!という流れで行き着いたのです。
大学職員の場合、公務員試験のように明確に試験で足切りされない(志望動機や面接での総合評価の場合も多い)というのが、魅力的でした。
これは、忙しい社会人が中途採用を受ける上での大きなメリットです。
デメリットとしては、学校事務を小中高勤務とした場合、学校法人として大学を持っていない場合、勤務地が限定的すぎる(=人間関係がめんどくさそう)ということは挙げられます。
閉鎖的な世界ではあるので、人間関係に悩みやすい・・・というひとには正直オススメしません。
逆に、今の上司からの詰めやノルマに比べたら余裕そうじゃんという人には向いている仕事です。
そのなかでも、おすすめは、大学を持っている学校法人勤務の学校事務(=主に大学職員)。
小中高単体では、儲かりません。
大学があることによって、大きな学費収入を得ることができますから、非常に安定していると言えるのです。
弊ブログからは、2020年11月現在で89名が大学職員へと合格しました。きっかけを作ってくれる転職エージェントも一応、紹介しておきます。
このブログから407人が大学職員に内定しました
2024年4月までに
大学職員を目指せるエージェントのまとめ
弊ブログからは、2018〜2024年で407名が大学職員へと転職しました。
大学職員の転職は情報戦です。自分の知らないうちに求人が出ていることを避けないといけません。
弊ブログでの実績のある、合格者がみんな使っていたエージェントは2つだけですので、シンプルです。
早めの登録と活用がポイントになります。
大学職員に転職できるエージェント
リクルートと並ぶ実績のあるエージェント
学校事務に転職したいと思ったら読む【仕事内容を理解して志望動機を書くコツ】

学校事務というと、一般的には「小中高勤務の事務職員」を指しますが、弊ブログがオススメするのは、大学を併設した学校法人の職員です。
小中高単体だと、1クラスあたりの生徒数が決められているため、それに応じた施設や教員を準備しないといけないので儲かりません。
大学の場合、教員1名に対して400名の一般教養科目などを実施できる為、コストパフォーマンスが良くなっています。
進学校の中高と、それほどでもないレベルの大学を持つ学校法人の場合、中高からその大学に内部進学するひとは殆どいないのが実情です。
ただ、その中高の進学実績をあげるための金を、大学が稼いで投入しているということが多々あります。
それだけ、大学を持つということは、集金構造としてのメリットが大きく、大学は本当に潰れないので、安定していると言えます。
そんな学校事務として、志望動機を書くには、どんなポイントを意識すれば良いのでしょうか?
重要なキーワードは2つ。
- 教員>事務職員というパワーバランスを理解した調整力
- 教職協働という言葉の理解
事務職員がやることは、教員が「教える・研究する」という環境に注力できるフィールドを整えることです。
意思決定権は教員が担っていますから、事務職員が前面に出て引っ張っていくことはほとんどありません。
ただ、教員はずっと教員をしている人間が多く、教えることに関してはプロフェッショナルですが、運営に関しては素人です。
これは、どっちが良い悪いという問題ではなく、専門性や職能の違いという感じでしょうか。
これ、小中高教員→大学職員への転職において、面接官である大学職員がイメージできないことの1つ。
なぜかと言うと、このようなイベントの要項は大学では事務が作り、教員の出勤体制を事前調整した上で教授会に上程するから。
小中高だと要項作りも教員の仕事なのでハードになる。 https://t.co/Zu5yTXnEJr
— 暇な大学職員@今年89名・累計165名が転職済 (@univadm) November 8, 2020
例えば、上記のTweetを事例に紹介してみる(小中高の場合はその多くを教員が担う違いはありますが)と、
- イベント運営におけるコンセプト立案→教員
- 実施日や場所、予算の提案と調整→事務職員
- 出勤教員などの実施体制策定→大学では事務職員、小中高では教員
- 当日の運営→大学では事務職員、小中高では教員
- 当日のステージ登壇なので主役的運営→大学、小中高ともに教員
このような役割分担で動くことが多いです。
その上で、どんな資格や適性が学校事務に求められているか、次の章で記載します。
学校事務の志望動機を埋める上で、求められている資格や適性って何?

- イベント運営におけるコンセプト立案→教員
- 実施日や場所、予算の提案と調整→事務職員
- 出勤教員などの実施体制策定→大学では事務職員、小中高では教員
- 当日の運営→大学では事務職員、小中高では教員
- 当日のステージ登壇なので主役的運営→大学、小中高ともに教員
例えば、イベント運営において、上記のような役割分担ですと先程ご説明しました。
その上で、学校事務の志望動機を書くには、どんな能力をPRすれば良いのでしょうか?また、必要な資格はあるのでしょうか?
まず、資格についての結論からお伝えしますと、資格は必要無いです。
資格としては、TOEICが高ければ良いのですか?という質問を相談用の無料LINE@でもよく頂きます。
ただ、弊ブログから累計165名(2020年11月現在)が合格した実績から見てみると、TOEICが高い=海外勤務や海外大卒というスペックの方も複数いらっしゃいますから、安易にTOEICに走るのは危険です。
TOEIC600点の方が、頑張って800点まで上げたとしても、次は日常的に仕事で英語を使っている人と競合するからです。
そのため、弊ブログでは大学職員という仕事をひたすら深く理解することに最も注力しています。
大学職員に転職|現役職員が書く161名内定のノウハウ【2020年版】
大学職員という仕事を深く理解する=教員と事務職員の関係性を理解する、仕事の進め方での教員と事務の役割分担を理解すると言い換えることができます。
大学職員に転職するには、前職での営業成績が1位でした!というような実績は必要ありません。
むしろ、実績がなくても、仕事を理解し、正しいルートで大学職員の求人を探し、エントリーシートを深めることができたひとが内定しています。
調整力やマルチタスク能力といった自らの能力をPRすることが重要なのです。
学校事務の志望動機の書き方を現役大学職員が解説【図解有り&コピペOK】

- 調整力
- マルチタスク能力
- コーディネート能力
これらが学校事務へ転職するうえで、必要なの能力であることは、弊ブロからが累計165名ほど大学職員へと転職したことから分かってきました。
それは、事務職員と教員の仕事の役割の違いに起因しています。
| 仕事の分担 | 教育 | 研究 | 事務仕事 | |
| 教員 | 主に所属する業務グループや委員会が決まっている | メインの仕事 | メインの仕事 | 基本的に関わらない |
| 事務職員 | 教員の教務分担においてアサインされる | 関わらない | 関わらない | メインの仕事 |
教員の場合、教育や研究がメインの仕事であり、そのサブとして、担当業務グループ(広報委員会やオープンキャンパス担当)が割り振られています。
ただ、事務職員の場合は、その教員の担当業務グループや委員会の運営補助がメイン業務となります。
つまり、事務職員は事務をすることがメイン業務であり、委員会開催やイベントに合わせた業務グループを運営(開催されるお膳立て)がミッションとなっているのです。
具体的には、会議日程開催の調整から場所の予約、会議がお昼の場合は昼食の手配といった事前事務から、主となる教員と打ち合わせを行って事前の議題整理、議案書の印刷や配布などが仕事となります。
多くの教員はその委員会の時間になったら会議室に来て椅子に座って意見を出すだけであり、実質的な運営はその委員会の主となる実務担当教員と事務職員に任されているのです。
そうなると、調整力やマルチタスク能力、コーディネート能力が必要な理由がおわかりになったかと思います。
私が事務職員として必要な能力は、調整力やマルチタスク能力、コーディネート能力だと考えます。特に、事務職員として大学(もしくは学校)の運営に携わりたいと考えたとき、案件毎にアサインされる教員を巻き込みながら目的の達成に向けて行動する必要があるはずです。具体的には、●●●(例:オープンキャンパス)の運営において、現在の仕事の(〜なエピソード)で培った●●●力を活かせると思います。特に、教員の場合は教育や研究をメイン業務として抱えていることから、事務職員が主導して行動することで、教職協働で(オープンキャンパス)の成功に向けて行動することができると考えます。
このように、事務職員が営業担当のようにバリバリと行動することはありませんが、教員を巻き込みながら教職協働で働いていきたいということをPRするのが重要なのです。
そして、更に具体的な事例(その大学が強みとするイベントや教育活動)を挙げながら、調整力などをPRすると、「事務職員の働き方を理解できているな」という評価を得ることができ、選考が進んでいきます。
正しい事務職員の仕事の理解、更にはそのためのエントリーシートづくりを行っていくことが内定への重要なプロセスです。
それを繰り返していけたことが、弊ブログから160名以上の大学職員への合格へ繋がったと感じています。
このブログから407人が大学職員に内定しました
2024年4月までに
大学職員を目指せるエージェントのまとめ
弊ブログからは、2018〜2024年で407名が大学職員へと転職しました。
大学職員の転職は情報戦です。自分の知らないうちに求人が出ていることを避けないといけません。
弊ブログでの実績のある、合格者がみんな使っていたエージェントは2つだけですので、シンプルです。
早めの登録と活用がポイントになります。
大学職員に転職できるエージェント
リクルートと並ぶ実績のあるエージェント